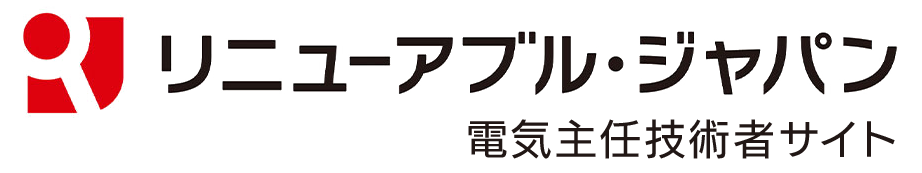リニューアブル・ジャパン株式会社の電気主任技術者がどのような働き方をしているのか?今回は、O&M本部 青森事務所にて、その環境を取材してきました。
青森事務所
後藤 和喜
第2種電気主任技術者
エネルギー管理士
入社理由について教えてください。
私は新卒でビルや学校等における高圧受電設備の保守運用を請け負う会社に就職し、仙台市で働いていましたが、再エネ事業に携わりたい!特別高圧設備の保守運用を経験したい!と思いRJに転職しました。
当時は、カーボンニュートラルという言葉が認知され始めた段階で、私自身もその流れを受けて再エネに興味を持ち、発電事業者側の立場で設備を保守管理したいと思ったことが転職の動機になりました。
様々な発電方式がある中で、どの発電事業に携わろうかと考えたときに、
震災のこと、自分の好きな釣りや自然環境のことを考えまして、どうせなら環境に良い発電事業に携わりたいと思ったのです。火力や原子力発電は今後も必要とされる方式ですが、効率よりも未来へ向けて可能性のある再エネ事業に関わることで、そういった未来あるものの黎明期に携わりたいと思いました。
教科書でしか見たことがなかった発変電の仕組みを現場で初めて見た時には興奮しました!
電気主任技術者の資格取得にあたり、どのような経緯があったか・難しさの違いなど教えてください。
電気主任技術者の資格は、在学中に三種を取得し、二種は社会人になってから取得しました。
三種から二種を取得するにあたり、技術知識のレベルも格段に上がり、とても難しくなります。
取り扱える設備の電圧が、5万ボルトから17万ボルトになるため、働ける環境も随分と変わります。
三種は中規模設備の仕事がメインとなりますが、二種となると超大型のビルや大規模太陽光・風力等の発電所となり全体の99%を見ることができます。一種は一部の事業場に限られるため、現在の自分にとっては二種でも十分に納得感を持って仕事をしています。
変電所での仕事はどのようなことをしていますか?
この変圧器で変電をして、送電線に連系して、電力が家庭に送られます。
電気主任技術者は保安の監督がメインの仕事なので、協力会社等への指示や管理をする立場になりますが、RJは試験検査業務なども内製化しているため、幅広い技術を兼ね備えた人材が揃っています。
所員が担当する青森地区は22箇所もの発電所があります。
–ヘルメットをまずかぶって、工具袋を腰にかけて、点検用の書類を持ち、周囲の状況に注意しながら作業を進めていく–
リニューアブル・ジャパンはどんな会社だと思いますか。
私が入社して特に感じたのが、個人の裁量が大きい会社だということです。
多少難しい業務や、若い年代ではやらせていただけないような仕事も、任せていただける会社だというのが一つ特徴としてあるのではないでしょうか。
成し遂げれば成長のスピードが早く、自分でもレベルが上がったなと思えるところに満足しています。
電気主任技術者としての「レベルが上がった」とはどのような変化でしょうか?
以前と比べて2つレベルが上がったと実感しています。一つは、チームをまとめる力がついたこと。もう一つは、的確な指示も出せるようになったことです。点検時の場合ですが、各点検・試験検査項目を自分で実施できるようになったことで、関わる人に具体的に指示できるようになったことです。
前職は新卒で入社し、4年と数ヶ月在籍していました。若手であったという立場もあり、基本的には上司や先輩の指示のもと働くケースが多く、責任が少なく楽なところはありましたが、指示を受けるだけで点検をしても、覚えられないんですよね。
先頭に立ちつつ責任を持つことや、これまで「成し遂げる」という感覚を持つことがなかったのですが、RJに入ってからはそれが変わりました。新しい会社というのもあり、人も前職ほど多くはないし、自分が先頭に立たなければいけないプレッシャーもありましたが、それを成し遂げることにより、現場をまとめる力と技術を習得することができました。
今は、大規模な点検の統括責任者を拝命することも多々ありますが、関係者をまとめて指示を出すことができています。
大きなトラブルもなく、無事に業務を遂行できていることには、とても満足しています。
RJでのこの3年間でスキルがついたと感じています。
イレギュラーが起こった経験があれば、それをどのように乗り越えたか教えてください
発電所で電気的な事故が起きて発電が止まってしまったことがあります。
そういった時も図面を読み解く力などを駆使、原因を解明した後に改修工事を施して、発電を再開する経験ができました。
自分が率先して担当し、何かトラブルがあれば、自力で先頭に立ってやってきました。
まずは自分が先頭に立つことが重要です。
理論的な面から原因を考えたりすることも重要で、実際の現場でも、資格で問われるような知識を駆使する現場での場面はかなりあります。
そういった経験は、どういう習慣や環境があってできたと思いますか?
学びの継続が一番大事だと思います。知識は数日の間を空けるだけで忘れていくので、毎日の継続が必要です。知識の定着については、現場で実際の設備など運用に携わることができる環境が大きいと思います。
現場に行けば見ることができますので、実際にものを見てどういった働きをするかを体で覚えれば、試験で問われても答えることができる。これが大きいです。自分自身で設備を運用した経験が大事です。
このような現場経験によって、電気主任技術者二種の資格を取ることができました。
電気主任技術者試験で問われる知識は、現場で使う知識とかなりリンクしているんですよ。資格を取りたい人が、現場で実際の運用を学びつつ座学の勉強と並行するのも効果的かもしれません。
今後のキャリアについて目標はありますか
RJは、再エネの発電所…太陽光がメインですが、再エネというと風力や水力、バイオマスなどもあります。
そういった複数の発電所に対して、いかなる場面においても、対処できるようになりたいなと考えています。
風力や水力もRJにはあるので、様々な現場に対して経験を積みたいです。電気的な業務・イレギュラーも含めて、幅広くできる技術者になりたいと思います。
RJに、目標を叶えられそうな環境はありますか
機会があれば、興味のある発電所などに勤務希望を出したいと考えています。
決まったローテーションはないものの、希望を出せば会社が向き合い考えてくれるんだろうなと感じています。裁量が大きく、希望したことをやらせて貰えている経験からそのように感じています。他の人たちを見ていても、地元で働きたいなどの理由で別の発電所に勤務地を変更しているケースもありました。
技術的に分からない箇所を聞いたり、待遇に対しての相談だったり、人生相談だったり、RJには相談できる環境が揃っています。
RJアカデミーについてですが、本社の講師から電気理論や系統工学等の講義を受講できる体制となっています。
また、研修施設には実際の現場と遜色ない研修設備が配備されており、操作等の体験が可能です。アカデミーで理論や保守運用技術を学び、現場で駆使することで、恵まれた環境のもと成長できています。
私も書籍等だけでは習得できない知識も講義によって理解できたりしています。RJで働いていると、バランスのいい技術者になれます。理論と技術のバランスが取れた教育体制になっていると感じています。
最後に伝えたいことがあれば教えてください。
新卒時のことを思い返すと、電気主任技術者の三種を取り、自信満々で迎えたスタートだったのですが、実際の設備を前にして、何かできるかというと何もできなくて、車の免許で例えると”学科はできたが実技できない”という状態でした。電気主任技術者は資格を取ることがゴールなのではなく、点検などの実務をこなせることが大切です。
それには、実際に現場経験を積める環境選びががおすすめです。
RJでは、アカデミーもあるし、現場で必要となる知識も学べます。
知識と技術の習得、さらには裁量を持ち活躍できる機会もあり、キャリアを積むとてもよい環境が揃っていると思います!ぜひ一緒に働きましょう。