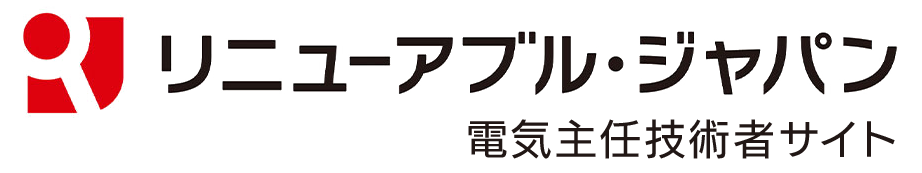資格は「道具」にすぎない。本当に問われるのは、その使い方
「電験三種を取った」
「次は電気主任技術者として働きたい」
その気持ちと努力は間違いなく価値のあるものです。
でも、それだけでは十分ではない時代が来ています。
企業が求めているのは、ただ資格を持っている人ではなく、
資格を使って創造的に考え、現場をよりよくできる人です。
再生可能エネルギー業界における電気主任技術者の仕事は、
まさにこの「創造性」が問われるフィールドです。
「電験=点検作業」という思い込みを壊す現場
電験三種を活かした仕事というと、
高圧設備の点検、測定、帳票作成などの保守業務を思い浮かべるかもしれません。
しかし、再エネの現場ではそれだけではありません。
・発電量が下がった原因を分析し
・システム設定を調整し
・今後の改善策を提案する
そんな「問題を見つけて、考えて、変えていく」ことが求められます。
たとえば、こんなシーン
太陽光発電所のPCSがたびたび停止していたある日。
数値上は異常なし。だが、過去のデータを照らし合わせると、「気温が高い日」だけ止まっていることが判明。
風通しを改善するために、現場でのファン交換と設備配置を提案。
その後、停止回数がゼロに。
このように、目に見えない問題の本質を突き止める仕事は、まさに技術者ならではのクリエイティブな営みです。
現場で働く人の声
「正直、前職では“資格持ってるから、点検だけやってればいい”と思ってた。でも、再エネ現場では“考えて提案しなきゃダメ”なんです。それが逆に、面白くなってきました」
(30代・太陽光発電所の保守担当)
「設備を動かすって、答えがないんです。こうすれば絶対よくなる、なんてことはない。でも、考えて試して、成果が出た時の達成感は大きいですね」
(40代・風力発電運用)
“資格を活かす”とはどういうことか?
「資格を活かす」という言葉があまりに曖昧に使われすぎています。
本当に資格を活かすというのは、
・その資格によって業務を許可されるだけでなく
・その知識とスキルを、現場の課題解決に応用できること
だと、再エネ業界では実感させられます。
電気主任技術者の業務範囲は、意外と広く、
・保安規定の改善
・トラブル傾向の可視化
・地域への情報提供
など、自分の発想で現場を変えていくことができるのです。
「受け身じゃいられない」から、面白い
再エネ業界では、設備の規模も場所も条件もバラバラ。
だからこそ、誰かの正解が自分の現場では通用しないことも多いです。
その中で「どうするか」を考え、自分なりの答えを出していく。
それは、受け身ではできません。
指示を待つのではなく、現場から課題を拾い、周囲と連携しながら解決していく。
自分の意志で動ける人にとっては、これ以上に面白い仕事はないかもしれません。
創造的な電験技術者に必要な視点
以下のようなスキルや姿勢を持つ人は、再エネ現場で特に活躍しやすいです。
| スキル・姿勢 | 説明 |
|---|---|
| データの活用力 | 過去の発電量やエラー履歴から改善点を発見できる |
| 提案力 | 現場に即した具体的な変更提案ができる |
| 対話力 | 設備業者・自治体・オーナーなど、さまざまな相手と交渉できる |
| 柔軟性 | マニュアル通りでは通じない現場に対応する思考力 |
| 好奇心 | 技術動向や設備の構造を探求する姿勢 |
「ただの保守点検」で終わらせないために
せっかく電験を取ったなら、
「点検して報告書を書くだけ」ではもったいない。
あなたのその資格には、
もっと人の役に立つ力があります。
もっと現場を良くできる可能性があります。
それを発揮できる場所が、再生可能エネルギーの現場にはあります。
「使い方次第」で、仕事はおもしろくなる
資格を持っていること。
それは、キャリアの“入り口”にすぎません。
本当に大切なのは、
その資格を「どう使うか」を自分で決めて動くこと。
再エネ業界には、その動きがダイレクトに結果につながる現場があります。
資格を活かすとは、自分の力で変えていくこと。
思った以上に、クリエイティブで、面白い世界が待っているかもしれません。