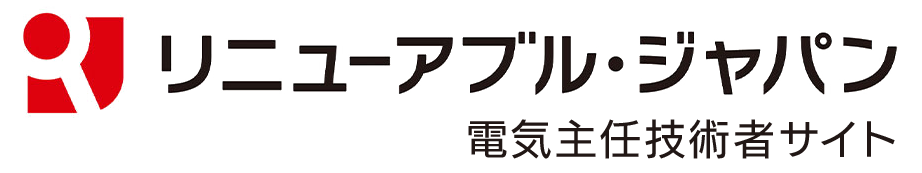「文系出身でも電気主任技術者になれるの?」「資格を取るのって何年もかかるんじゃ…?」
そんな不安を抱えている方にこそ知ってほしい、“20代だからこそ目指せる”キャリアの選択肢があります。
なぜ今「電気主任技術者」が注目されているのか
エネルギー転換の中心にいる存在
近年、再生可能エネルギー(再エネ)へのシフトが加速しています。太陽光発電や風力発電の導入が進む中、それを安全・安定的に運用するために必要なのが「電気主任技術者」です。
この資格者は、発電所や工場、ビル施設などで電気設備の保安を担う国家資格保有者。電気の専門家として、法律上必ず配置が求められています。
再エネ拡大によって新設される発電施設や設備が急増する一方で、資格保有者の高齢化や人材不足が深刻化。その結果、若手の電気主任技術者に注目が集まっているのです。
“人はいるのに足りない”?その裏側
資格はあるけど「実務経験」が足りない人が多い
電気主任技術者には、第一種〜第三種まで3つの区分があります。特に太陽光発電など比較的小規模な設備を管理するには「第三種電気主任技術者(通称:三種)」が必要です。
ただし、この資格は筆記試験に合格するだけでは就業できません。実際に主任技術者として働くには、**国が認定する“実務経験”**が求められます。
そのため、せっかく資格を取っても、実務経験を積む機会がないまま数年を過ごしてしまう人も少なくありません。つまり、資格を持っているだけでは“即戦力”にならない構造が、この業界の人手不足の背景にあるのです。
安定・高収入・社会貢献、3つの魅力
電気主任技術者が選ばれる理由とは?
20代で電気主任技術者を目指すことには、いくつかの明確なメリットがあります。
- 国家資格による安定性
電気主任技術者は「電気事業法」に基づいた法律上の資格。有資格者しか就けない仕事であり、常に一定のニーズがあります。 - 高めの年収水準
第三種であっても、年収は400万〜600万円のレンジが一般的。経験や保有種別、勤務地によっては年収700万以上も可能です。 - 再エネ分野での社会貢献性
太陽光や風力といった再エネ設備の運用管理を通じて、持続可能な社会を支えるという実感を得やすいのも魅力です。
20代のうちにこのルートを選べば、将来的に第一種・第二種へのステップアップも狙える長期的キャリアが築けます。
文系からでも始められる?未経験者のルート
資格取得と実務経験のステップを分解
文系や未経験から電気主任技術者を目指すことは可能です。必要なのは、正しい順序と選択です。
ステップ1:資格取得(第三種)
三種は電気に関する基礎〜応用レベルの国家試験で、以下の4科目があります。
- 理論
- 電力
- 機械
- 法規
合格率は例年10〜15%前後とやや難関ですが、市販テキストや講座を活用して独学で合格している人も多くいます。試験は毎年1回(9月頃)、全国で実施されています。
ステップ2:実務経験を積む
試験合格後は、「選任」と呼ばれる形で実際の電気保安業務に就き、実務経験を積む必要があります。ここでポイントとなるのが、電気保安法人や再エネ関連のベンチャー・スタートアップ企業。
こうした企業では、「見習い・補助業務」として経験を積ませながら、早期に主任技術者として選任してくれるケースもあります。また、地方の発電所やインフラ事業体では、若手登用を積極的に行っている地域も増えています。
ステップ3:中長期のキャリアアップ
実務経験を積んで数年が経つ頃には、第二種・第一種の受験資格も得られるようになります。また、経験をもとに保安管理業務の独立開業や、再エネ企業での技術マネジメント職といったキャリアの可能性も広がります。
今こそ、未来を支えるキャリアへ
「いつか」じゃなく「今」がチャンスの理由
電気主任技術者は、一部の専門職では珍しく「未経験から国家資格を取り、手に職をつけられる」数少ない仕事です。
特に再エネの伸びが続く今、20代のうちにこの分野に足を踏み入れることで、
- 実務経験を早めに積める
- 高齢化する業界の中で若手が重宝されやすい
- 安定しながらも社会課題解決に関われる
といったチャンスを掴むことができます。
キャリアの選択肢に迷ったとき、「電気主任技術者」という国家資格を土台にすることで、地方でも、都市部でも、再エネ企業でも活躍できるフィールドが広がっていきます。