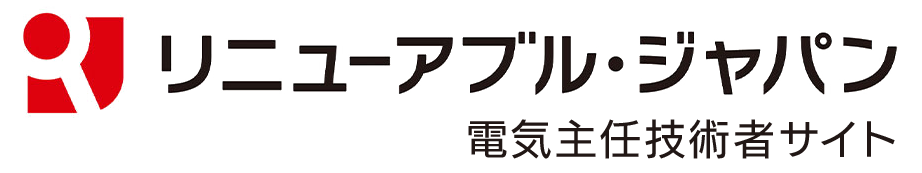電気主任技術者は、これからの時代も必要とされる仕事なのでしょうか?
結論から言うと、答えは「Yes」です。特に、再生可能エネルギー(再エネ)の拡大とともに、その重要性はむしろ高まっています。この記事では、再エネ時代における電気主任技術者の役割と、今後の展望について解説します。
再生可能エネルギーの導入が加速中
太陽光・風力・バイオマス発電などの増加
地球温暖化対策やエネルギーの地産地消を背景に、再エネ設備の導入は全国的に進んでいます。特に、太陽光発電や風力発電は中小規模の自治体や民間企業でも設置が進み、発電事業者の数も急増しています。
こうした設備も「電気工作物」に該当するため、法律上、一定規模を超える場合は電気主任技術者の選任が必要になります(電気事業法第43条)。つまり、再エネが広がるほど、電気主任技術者の需要も比例して高まるのです。
再エネ設備の“管理の複雑さ”に対応する役割
分散型電源・蓄電池・パワコンの理解がカギ
再エネの現場では、分散型電源や蓄電システム(蓄電池)、パワーコンディショナ(パワコン)といった新しい技術や機器の管理が求められます。これらは従来の受変電設備と異なり、発電量が天候によって変動するなど、管理の難易度が高くなっています。
電気主任技術者には、こうした設備の特性を理解した上で、安全・効率的に運用するスキルが求められており、まさに「進化し続ける技術者」であることが大切です。
脱炭素とエネルギー政策の中での存在感
国の目標達成に不可欠な人材へ
日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、電源の再エネ比率を拡大させる政策を進めています。こうした方針のもと、地域の再エネ導入や分散型エネルギー社会の実現において、電気主任技術者は不可欠な担い手です。
再エネ設備の新設・増設が進めば、保守管理や法定点検を担う技術者の役割はますます重要になり、電験三種以上の資格保有者には新たなキャリアのチャンスが広がっていくでしょう。
新しい働き方・新しいキャリアも生まれている
地域密着・複業型・外部委託の広がり
再エネの広がりとともに、働き方にも変化が生まれています。たとえば、地域の小規模発電所を巡回管理する外部委託型の仕事や、複数の事業所を担当するフリーランス的な働き方など、従来にはなかったキャリアモデルも登場しています。
企業と個人、自治体と技術者をつなぐマッチングサービスも増えており、場所や勤務形態にとらわれずにスキルを活かせる環境が整いつつあります。
「再エネ×電気主任技術者」はこれからのスタンダード
学び続けることで、未来はもっと広がる
再エネが社会のインフラになるこれからの時代、電気主任技術者は“守る人”から“支える人”へと役割が進化しています。設備の安全を守るだけでなく、エネルギーの使い方そのものを考える視点が求められています。
制度や技術の変化に応じて学びを重ね、変化をチャンスに変えていく──そんな姿勢が、これからの電気主任技術者に必要とされる力です。