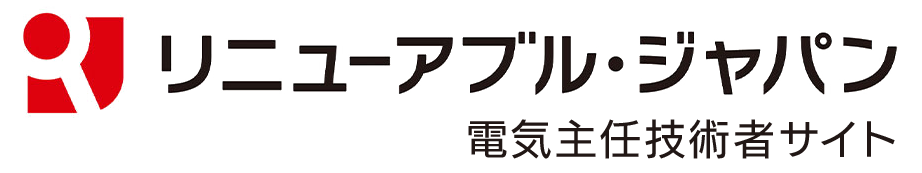電気主任技術者として働く日々の中で、すべての作業が“当たり前”になっていませんか?
その「慣れ」が油断を生み、事故やトラブルに繋がることがあります。
本記事では、実際の現場で起きたヒヤリ・ハットや事故事例をもとに、保安規定の重要性とリスク対策のヒントを整理します。
起きた事故にはすべて「原因」と「兆し」があった
ほんの一手間が命を守ることになる
例えばある事業所で発生した感電事故。
電源を落としたと思い込んで作業を開始し、絶縁不良のケーブルに触れてしまったのです。
調査の結果、「手順書の確認不足」と「絶縁抵抗の測定未実施」が原因でした。
このような事故は、作業前の確認プロセスが機能していれば、未然に防げたはずです。
保安規定は「守らせる」ものではなく「守られる」ためのもの
誰のためのルールかを、いま一度見直して
保安規定は法令で義務付けられたものですが、それ以上に「現場の安全文化」を形づくる軸になります。
しかし、形式的に整備されているだけで、実態として運用されていない現場も少なくありません。
たとえばこんな経験はありませんか?
- 「規定に書いてあるけど、現場では誰も実践していない」
- 「手順書が古く、実態と合っていない」
- 「新任者への教育が口伝えになっている」
保安規定は“活きたルール”であってこそ意味があります。
そのためには、年に1度の見直しと、全スタッフへの再周知が不可欠です。
トラブルが起きたあとに共通する「5つの後悔」
事故を経験した人が語るリアルな反省
実際にトラブルを経験した電気主任技術者の声を集めると、以下のような後悔がよく見られます。
- 「いつもの手順を省略しなければ…」
- 「“まあ大丈夫だろう”が命取りだった」
- 「忙しくてチェックを怠った」
- 「記録をつけていなかったから原因が曖昧に」
- 「あのときもう一言、声をかけていれば…」
これらは決して特別なケースではなく、どこの現場でも起こり得ることです。
こうした声に耳を傾け、自分の現場に置き換えることが、最大の予防策になります。
ベテランも新人も「確認する文化」が組織を守る
プロ意識とは、“ミスを前提に”動けること
どんなに経験豊富でも、人間である限りミスは避けられません。
だからこそ、複数人でのダブルチェック、作業前後の声かけ、記録の共有が不可欠なのです。
“属人化した手順”は、事故リスクを高めます。
たとえ時間がかかっても「確認・記録・報告」を徹底することが、結果的にトラブルを防ぎ、組織全体の信頼につながります。
今日から始められる3つの“リスク対策習慣”
小さな習慣が未来の事故を防ぐ
忙しい現場でも、以下の3つの行動はすぐに始められます。
- 作業前に「声に出して」チェックリストを確認する
- 現場で違和感を覚えたら「その場で立ち止まる」
- 終了後に「今日の気づき」を一言でメモする
どれも簡単ですが、これを毎日繰り返すことで、チーム全体の保安意識が高まっていきます。
保安は“日々の地味な積み重ね”がすべて
何も起きない日こそが、あなたの成果
事故は「注意したから起きなかった」のではなく、「注意し続けたから起きなかった」もの。
何もトラブルが起きない日常こそが、あなたの専門性と責任感の証明です。
今日も安全第一で現場に立ちましょう。