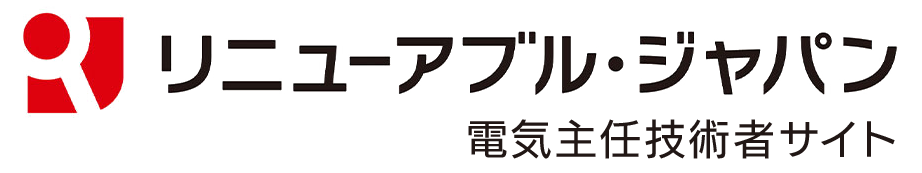「電験三種ってやっぱり難しいの?」
「理系じゃないと無理なんじゃない?」
そんな不安を抱えている人は多いでしょう。
確かに電験三種(第三種電気主任技術者試験)は、合格率10〜15%前後の難関資格です。しかし、未経験から挑戦して合格した人も数多くいます。
今回は、試験の特徴と難易度、そして未経験合格者の勉強法をわかりやすくまとめました。
電験三種とは?試験の基本情報に触れてみよう
国家資格の入口
電験三種は、電気主任技術者になるための登竜門。合格すれば全国どこでも「第三種電気主任技術者」として活躍できます。
試験科目
- 理論
- 電力
- 機械
- 法規
4科目すべてに合格する必要があります。科目合格制度があり、一度合格した科目は翌年以降も有効なので、数年かけて合格を目指す人も多いです。
合格率
例年10〜15%前後。数字だけ見ると難しいですが、正しい勉強法を実践すれば未経験からでも十分合格可能です。
未経験から挑戦して難しいと感じるポイントの例
数学・物理の基礎不足
文系出身者にとって、オームの法則や交流回路などの基礎知識が最初の壁。
ただし、高校レベルの基礎から学び直せば十分対応可能です。
試験範囲の広さ
理論・電力・機械・法規と分野が広く、勉強時間を効率的に配分する工夫が必要です。
継続学習の難しさ
社会人にとって最大の課題は「勉強時間の確保」。毎日コツコツ続ける習慣化が合否を分けます。
未経験から合格した人の勉強法はこれ!
1. 過去問中心の学習
合格者の多くが口をそろえるのは「過去問を繰り返すことが最重要」。
- 過去10年分を最低3周以上
- 問題を解くだけでなく、解説を理解するまでやり込む
- 出題傾向を把握し、得点源にする
2. 参考書・教材の使い分け
- 入門書で基礎理解
- 過去問集で演習
- 苦手分野は専門書や動画解説で補強
特にYouTubeや有料動画講座を活用して「わからない部分を視覚的に理解する」方法は未経験者に有効です。
3. 学習スケジュールの工夫
合格者の平均勉強時間は500〜1000時間。
1日2時間ペースなら1年、1日1時間なら2年計画で合格を狙えます。
- 平日はスキマ時間にインプット
- 休日は過去問演習でアウトプット
- 科目合格制度を利用して2〜3年計画もOK
4. 模試や直前演習で本番慣れ
本番で緊張して実力が出せないのはよくある失敗。模試や直前予想問題を解くことで、試験時間配分や解く順番の戦略を身につけられます。
5. 仲間・コミュニティの力を借りる
独学は挫折しやすいもの。SNSや勉強会で仲間を作ると、モチベーションを維持しやすく、情報交換もできるので合格率が上がります。
未経験者が挫折しないための勉強のコツ
- 完璧を目指さない:6〜7割取れれば合格ライン
- 基礎を飛ばさない:オームの法則・三相交流は必ず理解する
- 毎日触れる:短時間でも「勉強習慣」を切らさない
- 苦手は捨てない:部分点を積み重ねる戦略が重要
電気主任技術者は難しい。けど「戦略次第」で合格できる資格。
電験三種は確かに難関試験ですが、
- 過去問中心の学習
- 基礎の徹底理解
- 学習時間の計画化
- 仲間や教材の活用
これらを実践すれば、文系・未経験からでも十分に合格可能です。
「難しいから無理」ではなく、
「戦略的に挑めば誰でも合格できる」。
合格を目指しましょう!