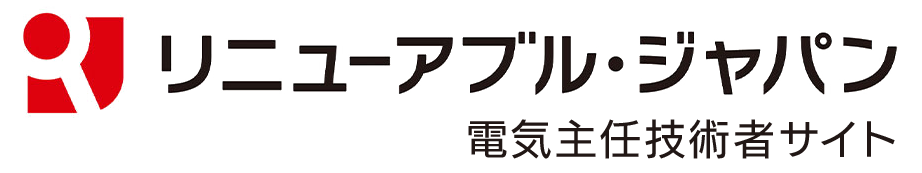再エネ系求人の裏側。なぜ今、電気主任技術者が“争奪戦”なのか?
再生可能エネルギー業界で、いま「電気主任技術者」が熱く注目されています。
特に地方や中規模の発電所では、経験者・有資格者の“取り合い”すら起きている状況です。
この資格になぜこれほどまでの需要が集まっているのか、その背景をやさしく解説していきます。
再エネの急拡大が技術者不足を加速させている
電気主任技術者は安全・安定の要
電気主任技術者とは、電気設備の保安を担う国家資格者です。法律(電気事業法)に基づき、事業所の設置者は「選任」する義務があり、工場や病院、商業施設、発電所など幅広い現場で必要とされます。
特に、太陽光・風力・バイオマスといった再エネ系の発電所ではこの資格者が不可欠で、近年その必要性が一段と高まっています。実際、再生可能エネルギーの導入量はこの10年で飛躍的に増加し、2024年度には全国の設備容量が1億kWを突破する見通しです(資源エネルギー庁「再生可能エネルギー導入量」より)。
その結果、各地で「電気主任技術者が足りない」という声が頻発。特に太陽光発電所の新設やO&M(運用・保守)を担う企業では、即戦力として資格保有者を求める傾向が強まっています。
人材不足の本当の理由は“数”だけじゃない
資格者はいても“選任できる人”が少ない
「資格者がいるのに人が足りないの?」という疑問を持たれるかもしれません。実際、電気主任技術者の免状保有者は全国に多数いますが、需要と供給がかみ合っていないのが現実です。
その理由の一つは、実務経験を重視する業界特性にあります。たとえば第三種電気主任技術者の資格は比較的取得しやすいですが、現場経験が乏しいと、選任要件を満たさないことも多く、即戦力としてカウントされないケースが多いのです。
さらに、再エネ施設が地方に集中している一方で、技術者は都市部に多く居住しており、地理的なミスマッチも課題となっています。結果として、条件が合致する人材が非常に限られており、「取り合い」になっているのです。
電気主任技術者が再エネ業界で重宝される理由
O&M現場で求められる“安定運用”スキル
電気主任技術者は、設備の安定稼働と事故防止に直結する職種です。再エネ業界では、太陽光パネルや風車など“見えにくい場所”に設置されることが多く、異常を見逃さずに保守点検できる経験者は貴重な存在です。
加えて、電力自由化により新規参入企業が増えた結果、それぞれが自社で技術者を確保する必要が出てきたことも争奪の背景です。特に、外部委託ではなく“自社選任”を目指す企業は年々増えており、採用競争は激化の一途をたどっています。
安定・高収入・社会貢献という三拍子そろった職業
再エネ業界ならではの働きがい
技術者不足という現実は、逆にいえば「必要とされる職業」であるということ。電気主任技術者として働くことは、安定収入やキャリアアップの面でも多くの魅力があります。
たとえば、再エネ企業に転職した場合、年収は500〜700万円程度が相場。マネジメント層や設備全体を統括できるポジションになれば、800〜900万円を超えるケースも珍しくありません(参考:https://www.rn-j.com/business/om/denken/re-jobchange-40s)。
また、社会課題とされている脱炭素やSDGsへの貢献を、仕事を通じて実感できる点もモチベーションに繋がります。「自分の仕事が未来の環境に貢献している」と実感しながら働けるのは、電気主任技術者ならではの特権かもしれません。
未経験からでも目指せる可能性がある
文系出身・異業種転職でも大丈夫
「でも自分は文系だし、電気のことは難しそう…」と不安に思う方もいるでしょう。ですが、近年では文系出身者や異業種からの転職者も増えており、最初の一歩さえ踏み出せれば、十分にキャリアを築くことができます。
国や業界団体も人材育成に力を入れており、試験制度の見直しや研修支援制度、OJT制度なども整ってきています。また、東京電気管理技術者協会では「未経験者向け説明会」を定期開催しており、現場のリアルな話を聞くことが可能です。
さらに、実務経験を積むための「選任補助」や、外部委託先で経験を積むという手段もあります。最初から完璧である必要はなく、“現場に出て学ぶ”という姿勢が何よりも重要です。
「争奪戦」はキャリアの好機に変わる
再エネ×国家資格=未来志向の選択肢
ここまで見てきたように、電気主任技術者の“争奪戦”は単なる人材不足ではなく、再エネ市場の急成長、制度的要請、そして専門性の高さが重なった結果です。
だからこそ、未経験でも国家資格を活かしてキャリアを築きたい、社会に貢献しながら働きたい、安定とやりがいを両立したい――そんな人にとっては、まさに今がチャンスなのです。
未来をつくる再エネ業界で、あなたの力が求められています。