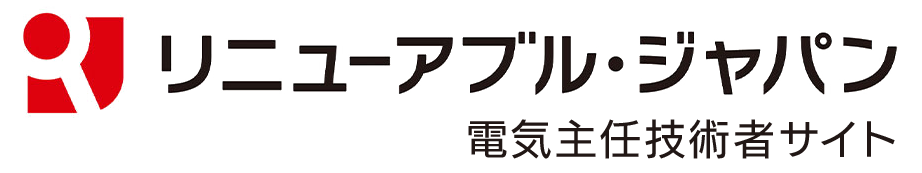電験三種で年収600万円は現実的なのか?
資格取得後、よく耳にするのがこの質問です。
「電験三種って、年収どのくらいもらえるの?」
「再エネ業界って儲かるの?」
この疑問に、現場の実態・企業の求人情報・キャリアパスなどをもとに、なるべく具体的に答えていきます。
結論からいえば、年収600万円は十分に現実的です。
ただし、そのためには「資格+〇〇」が必要です。
再エネ業界での電気主任技術者の給与水準
再生可能エネルギー業界の電気主任技術者の年収は、経験や企業規模によって幅がありますが、おおよそ以下の水準が目安になります。
・実務未経験者(20代前半)
年収350〜450万円
・経験2〜5年(選任補助・保守メンバー)
年収450〜550万円
・経験5年以上(主任技術者として選任)
年収550〜700万円
・マネージャー・統括保安監督者クラス
年収700〜900万円
つまり、実務経験を積み、選任技術者として責任あるポジションを担えば、年収600万円に到達するのは難しくありません。
給与に影響する3つの要素
1つ目は「保有資格」
電験三種に加え、電験二種・一種を持っていれば、より高圧の設備にも対応でき、年収アップにつながりやすいです。
2つ目は「選任実績」
実務経験の中でも、保安監督者としての“選任”経験があるかどうかは非常に大きな判断材料になります。これは単なる点検員よりも責任が重く、その分報酬も上がります。
3つ目は「兼任件数」
遠隔監視の発展により、1人で複数の発電所を兼任するスタイルが一般化しています。3〜5件の案件を管理している人もおり、その分手当や委託料も増えます。
どんな人が600万円を実現しているか
30代前半、電験三種+実務経験5年。
全国にある5件の太陽光発電所を兼任し、報酬は月額45万円+賞与で、年収ベースで600万円を超える。
40代前半、風力発電設備における統括主任技術者。
年収は720万円、年俸制。トラブル時の即応義務ありだが、普段はリモート主体で業務をこなしている。
50代、定年退職後に再エネ系企業に再就職。
電験二種+業務委託契約で、月額40万円超。年収換算で480万円以上を継続的に確保している。
このように、キャリアの積み方や雇用形態によっては、600万円以上の年収を実現している人は多数います。
再エネ業界の報酬体系の特徴
再エネ系の企業や保守運用会社では、以下のような制度や特徴が見られます。
正社員雇用の場合、基本給に加えて資格手当・危険作業手当・管理手当などが上乗せされる。
業務委託契約(兼任型)の場合は、月額契約+成果報酬制となるケースもあり、件数や対応力によって年収は変動します。
また、ベンチャー企業やスタートアップでは、成果を出せば早期に昇格・昇給することも可能で、裁量と責任が収入に直結します。
年収だけでなく、コスト面にも注目
年収アップを目指すうえで見落とされがちなのが、「生活コストの違い」です。
再エネ発電所は地方に多く、都市圏よりも物価や家賃が安い傾向にあります。
都心で年収600万円と、地方で年収500万円では、実質的な可処分所得が同程度になることも珍しくありません。
つまり、「収入×生活費」のバランスで考えれば、地方勤務の再エネ案件には非常に高いコストパフォーマンスがあるのです。
年収600万円を目指すなら、どんなステップを踏むべきか
まずは電験三種を活かして、保守や巡回管理業務に携わること。
次に、保安規定や点検記録を自分で作成・改善できるレベルに育つ。
その後、複数拠点を任されたり、新設プロジェクトに携わることで、収入アップのチャンスが広がります。
重要なのは、「点検するだけ」ではなく、「責任を持ち、改善できる人材」になること。
その信頼が、報酬に反映されていきます。
安定性と成長性を兼ね備えた電験三種を活かして年収600万円を実現
「資格を持っているだけで600万円稼げる」
そんな甘い話は、どの業界にも存在しません。
でも、正しく経験を積み、適切な職場を選べば、
電験三種を活かして年収600万円を実現するのは、決して夢ではありません。
再エネ業界は、安定性と成長性を兼ね備えたフィールドです。
働き方を工夫し、責任あるポジションを目指せば、
資格を“食えるスキル”に変えることは、きっと可能です。