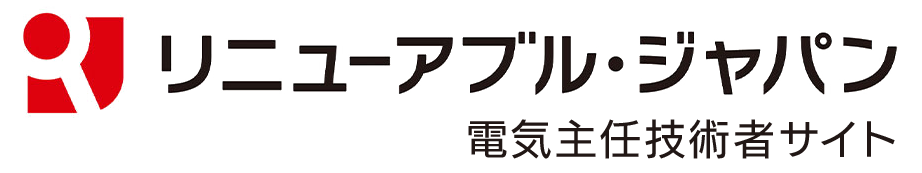「現場仕事=毎日出社」は、もう古い?
電気主任技術者といえば、毎日発電所に通って点検・監視・記録を行う「現場仕事」のイメージが強いかもしれません。
しかし近年、再生可能エネルギー業界では**“リモート×現場”のハイブリッドな働き方**が急速に広がっています。
特に注目されているのが、「週1回だけ現地巡回、あとはリモートで対応する」というスタイル。
この柔軟な働き方は、技術者のライフスタイルにも、業界の人材流動性にも、大きな影響を与え始めています。
どうして可能になったのか?背景にある3つの進化
1. 遠隔監視システム(SCADA等)の普及
各発電所に設置された監視装置が、発電量・異常履歴・機器状態をリアルタイムで通知。
ネット環境があれば、自宅やコワーキングスペースでも状況把握が可能に。
2. O&M(運用保守)体制の整備
発電所の保守業務を代行する専門会社の台頭により、主任技術者は監督・記録管理・判断といった“上流”に専念できるように。
3. 複数拠点兼任の一般化
1人の技術者が複数の太陽光発電所を選任し、効率よくスケジューリングする働き方が広がり、「毎日通う」必要性が薄れてきている。
これらの要素が重なり、従来の「現場に毎日張り付く」勤務スタイルが変化しつつあります。
実際にどんな働き方?
「週1現場・週4リモート」というスタイルの実例をご紹介します。
- 月曜:自宅からSCADAを確認。異常なし。点検予定の設備資料を整理。
- 火曜:現地巡回。点検項目に従い絶縁測定・開閉器確認・ファンの作動確認を実施。
- 水曜:点検記録をクラウド上で報告書にまとめ、オーナー企業に提出。
- 木曜:過去の異常履歴を分析。次回点検の重点項目を抽出。
- 金曜:必要に応じて業務委託先とZoom会議。点検結果の共有や改善提案など。
このように、現場作業は週1〜2回、あとは「監督・判断・記録・改善提案」が中心という働き方が増えているのです。
メリットは?
自由度の高いスケジューリング
子育てや介護をしている人でも、無理のないスケジュールを組みやすい。
地方在住でも都市部案件に関われる
発電所は地方に多いが、リモートで首都圏のクライアントとやりとりできるため、居住地を選ばない。
キャリアの幅が広がる
現場のみに依存せず、技術提案・改善指導・データ分析など、より専門的な仕事に集中できる。
一方、気をつけたい点も
この働き方が可能になるためには、一定の前提条件があります。
- 自らの判断で現場対応の可否を決められるスキル
トラブルの兆候をログから見抜き、現場に行くか否かを的確に判断できる力が必要です。 - 記録・報告の正確さとスピード
書類や報告業務が軽視されると、遠隔体制の信頼性が損なわれてしまいます。 - 緊急対応のフロー整備
現地での急なトラブルに備えて、対応可能な人員・業者との連携体制を持っておくことが重要です。
柔軟な働き方には、高いプロフェッショナリズムが求められるという点を忘れてはいけません。
求人でも「リモートOK」の記載が増加中
再エネ業界の求人を見ていると、「在宅勤務可」「フルリモート可」「現地巡回は月1〜2回」などの文言が目立ち始めています。
特に、次のようなポジションでこうした傾向が強くなっています。
- 太陽光発電所の保安監督者(外部選任)
- O&M企業の技術責任者
- 再エネデベロッパーの技術部門(兼任あり)
また、独立系の電気主任技術者として、複数案件を業務委託で受け持つスタイルも人気です。
「毎日現場」もテクノロジーと業界の進化によって変化
かつては「毎日現場」が当たり前だった電気主任技術者の仕事も、テクノロジーと業界の進化によって変わりつつあります。
週1現場、週4リモート。
それは“楽をする”ためではなく、より効率的に、より高度に現場を支えるための働き方です。
家庭やライフスタイルとの両立を考える人にも、キャリアアップを目指す人にも、
この柔軟な働き方はきっと、次の一歩を踏み出すきっかけになるはずです。